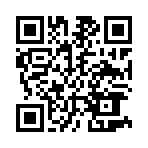農耕具ワークショップ
2016/10/09
本日は博物館の収蔵品の民具を使って脱穀体験!
ふだんは見るだけの道具を実際に使って、稲わらからモミを取り、玄米にするまでをやってみます。
まずはセンゴクドオシでワラからモミを取ります。
モミは丁寧に集めて・・・

トウミを使って、モミに混じったワラなどのゴミを取り除きます。
右側のハンドルをぐるぐる回すと、中の羽根板が風を生んで、上から入れたモミが落ちる際に
ゴミを風で吹き飛ばします。
日本では江戸時代から使われていたようですが、生まれは中国。世界中に同じような形の農具が広まっているようです!
現代も金属のトウミが、豆や穀類の仕分けに使われています。
完成された形なんですね!

ごみを取り除いたモミは、キスルスで擦り、お米からモミ殻を取ります。
二人で力を合わせて左右に引っ張ると、キスルスの間からぽろぽろとお米が出てきます!

またトウミにかけて、ごみとモミ殻を風で飛ばすと、きれいな玄米がでてきました~!

最後にマンゴクドオシで大きさの選別をして、できあがり!
ご希望の方には、脱穀したお米をお持ちいただきました。
お家のお米に混ぜて炊いてみてね。

毎日食べているお米ですが、口に入るまでいろんな作業がありました!
どれだけ手がかかっているかを体験すると、一粒一粒がありがたいですね。
次回の手仕事のじかんは、「ワラで作るなべ敷き」
毎回大好評のワラ細工、今シーズン1回目はワラを編み込みながらドーナツ形に仕上げる「編み込みタイプ」のなべ敷きです。
お鍋が活躍する冬に備えて、おひとついかがですか?
日 時 10/23(日)13:00~16:00
材料費 500円
詳細はこちらお気軽にご参加ください!
ふだんは見るだけの道具を実際に使って、稲わらからモミを取り、玄米にするまでをやってみます。
まずはセンゴクドオシでワラからモミを取ります。
モミは丁寧に集めて・・・

トウミを使って、モミに混じったワラなどのゴミを取り除きます。
右側のハンドルをぐるぐる回すと、中の羽根板が風を生んで、上から入れたモミが落ちる際に
ゴミを風で吹き飛ばします。
日本では江戸時代から使われていたようですが、生まれは中国。世界中に同じような形の農具が広まっているようです!
現代も金属のトウミが、豆や穀類の仕分けに使われています。
完成された形なんですね!

ごみを取り除いたモミは、キスルスで擦り、お米からモミ殻を取ります。
二人で力を合わせて左右に引っ張ると、キスルスの間からぽろぽろとお米が出てきます!

またトウミにかけて、ごみとモミ殻を風で飛ばすと、きれいな玄米がでてきました~!

最後にマンゴクドオシで大きさの選別をして、できあがり!
ご希望の方には、脱穀したお米をお持ちいただきました。
お家のお米に混ぜて炊いてみてね。

毎日食べているお米ですが、口に入るまでいろんな作業がありました!
どれだけ手がかかっているかを体験すると、一粒一粒がありがたいですね。
次回の手仕事のじかんは、「ワラで作るなべ敷き」
毎回大好評のワラ細工、今シーズン1回目はワラを編み込みながらドーナツ形に仕上げる「編み込みタイプ」のなべ敷きです。
お鍋が活躍する冬に備えて、おひとついかがですか?
日 時 10/23(日)13:00~16:00
材料費 500円
詳細はこちらお気軽にご参加ください!